新しいエネルギーマネジメントの仕組み(熱電EMS)

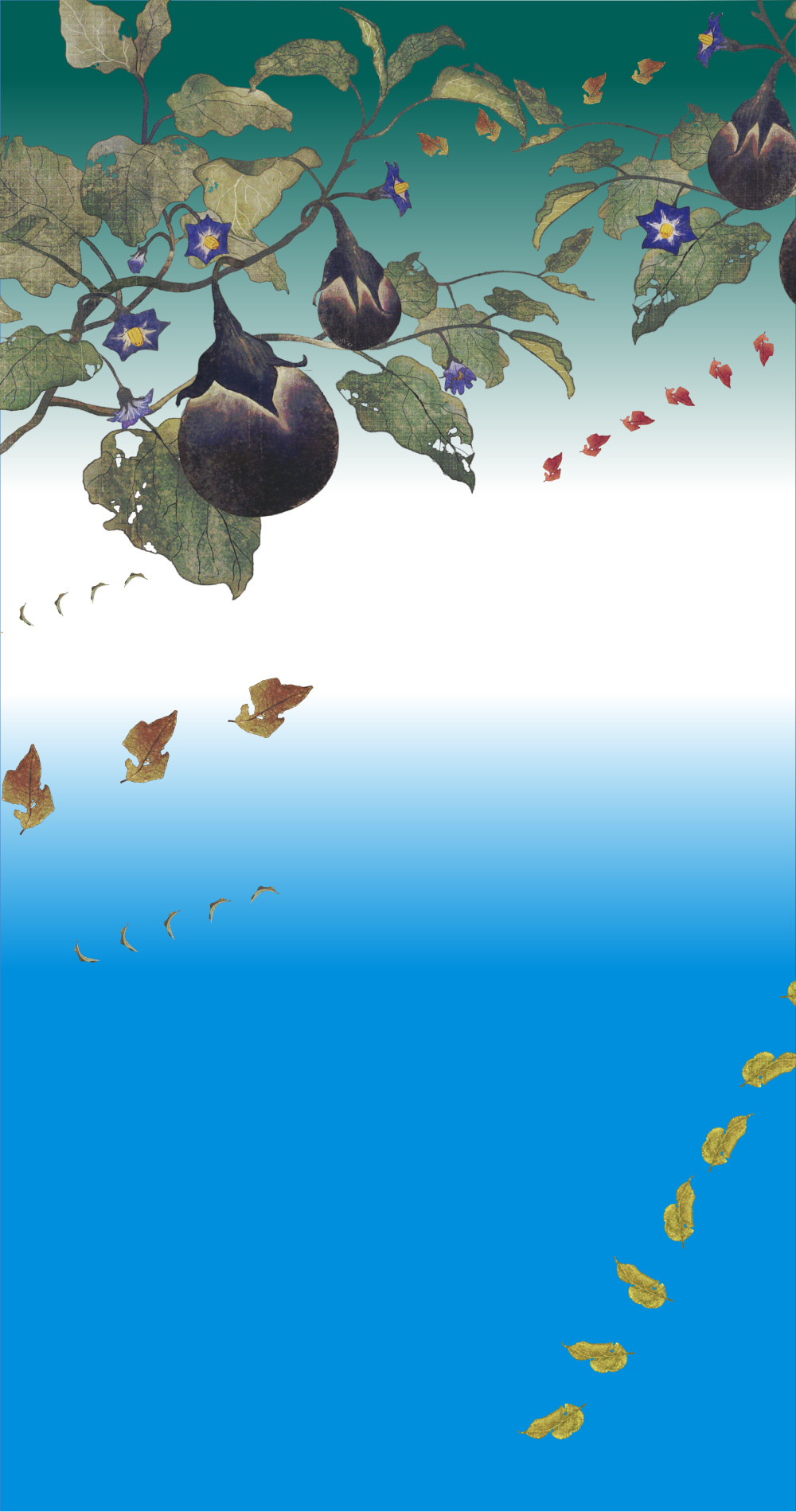




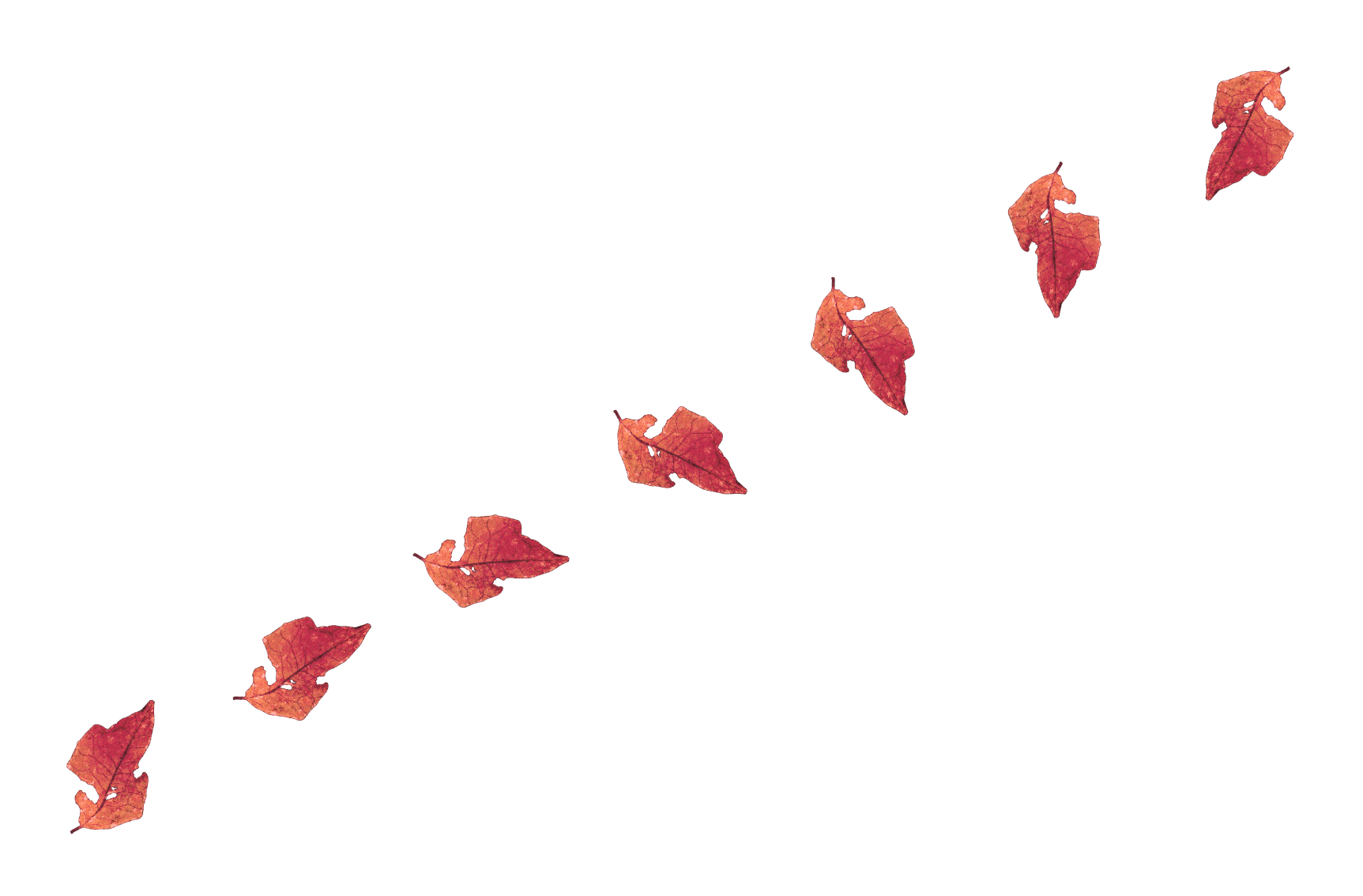


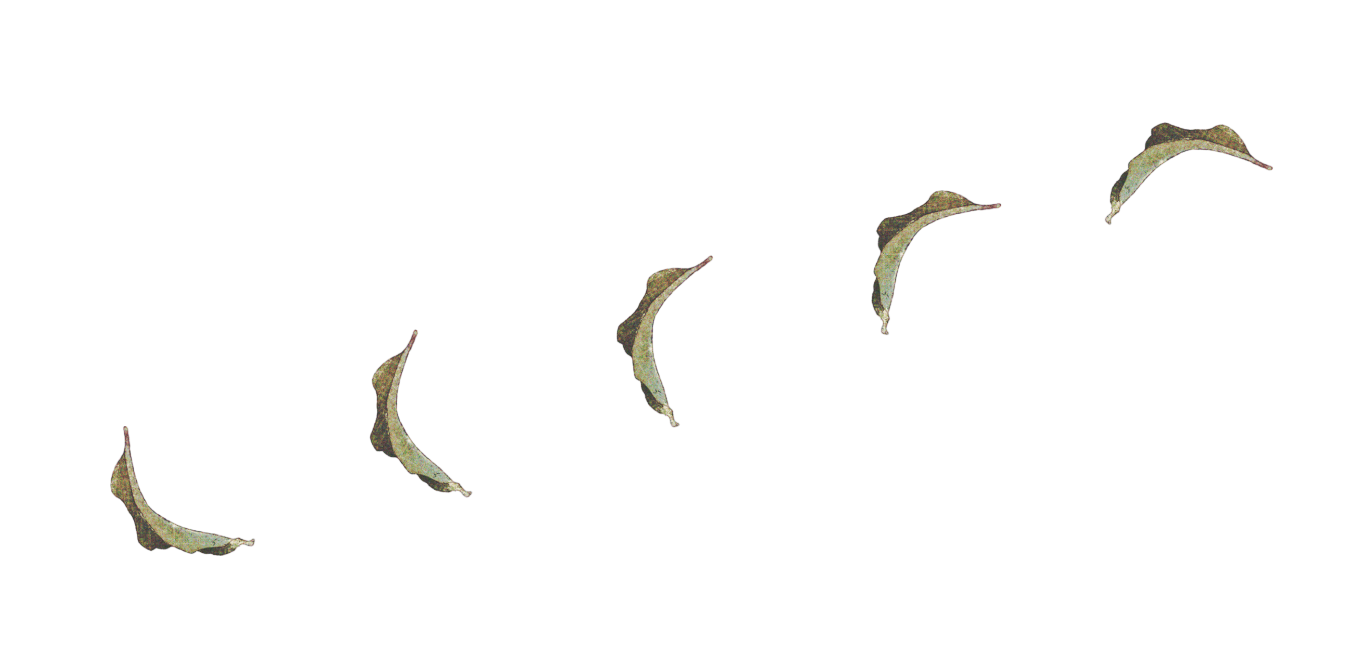




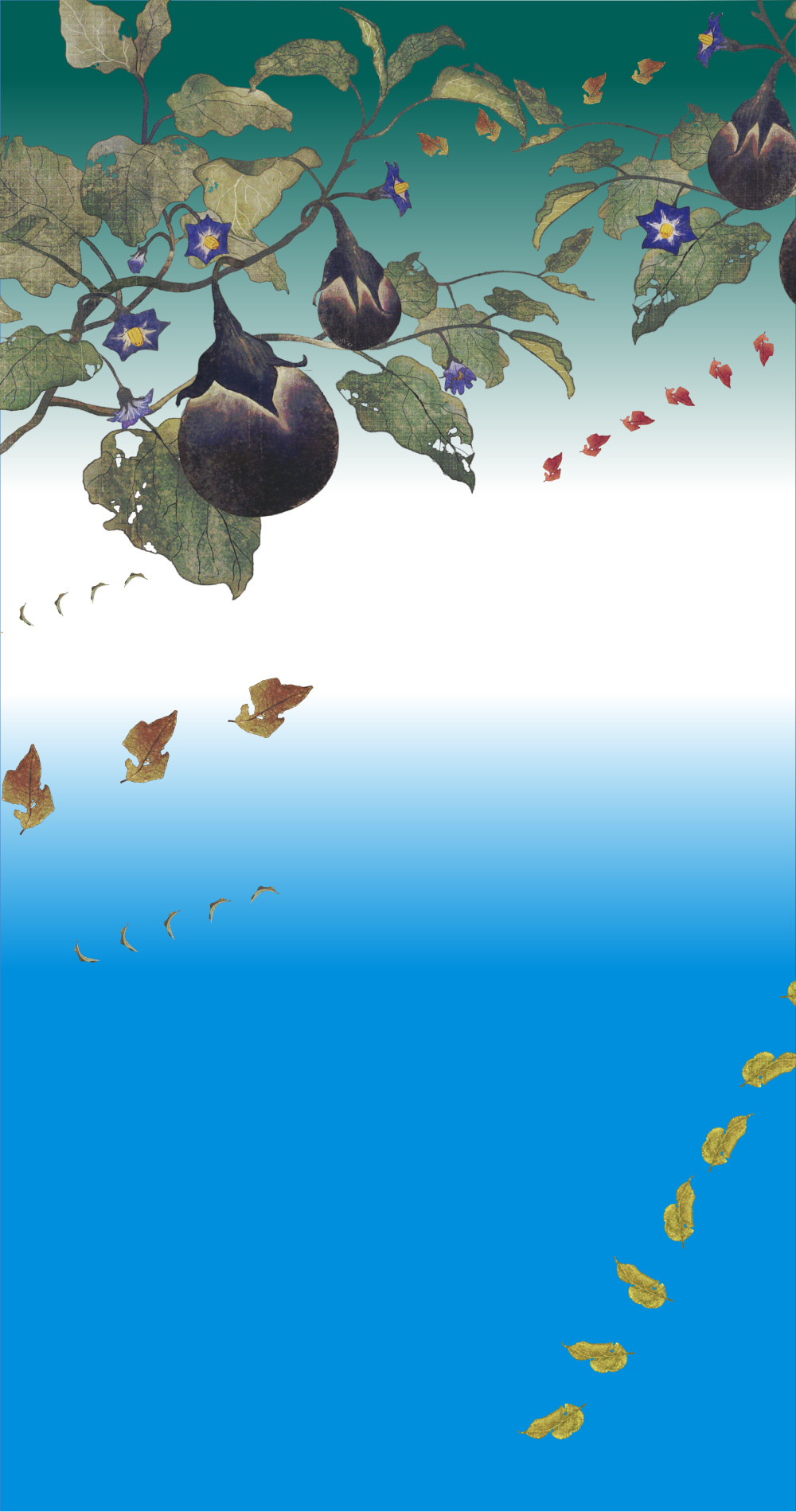




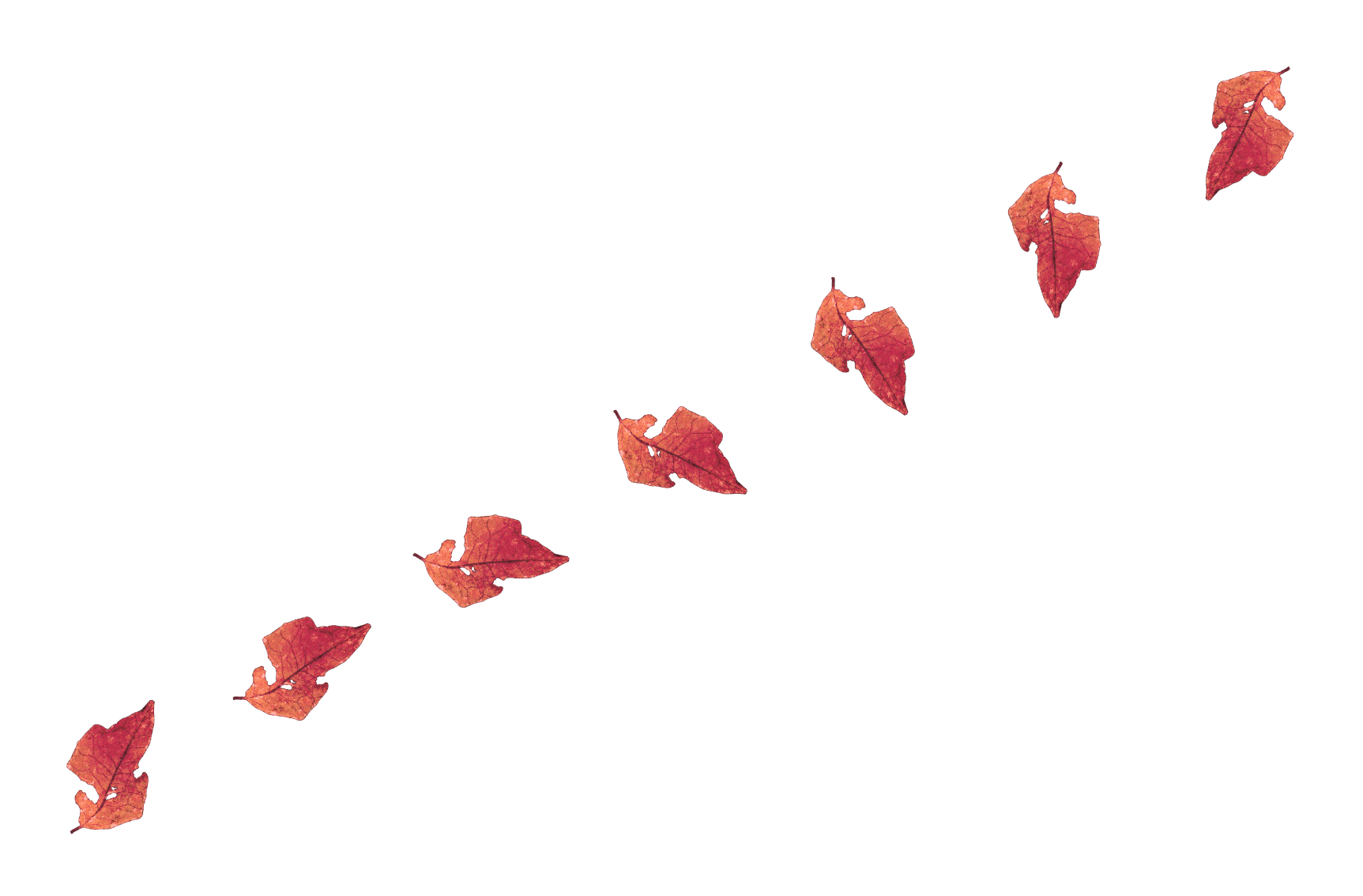


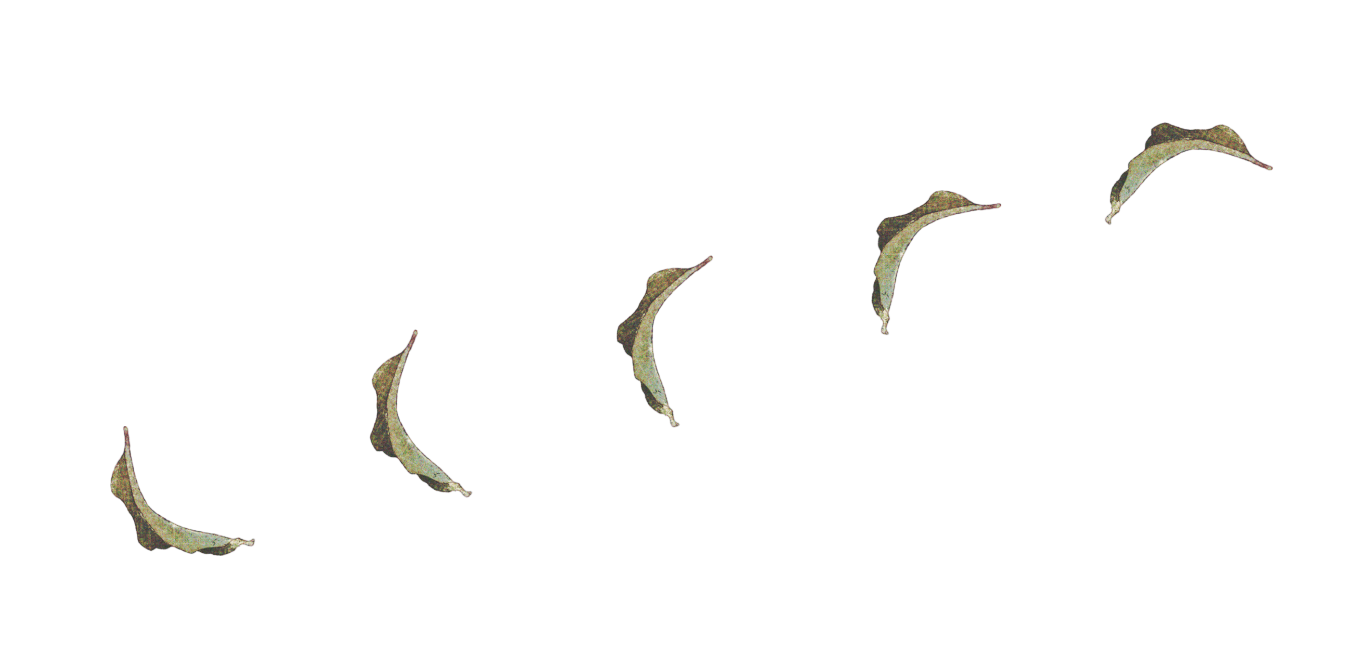



3期目となるWild Windでは、今年度も新規事業の創出において、パートナーを募集します。
三菱マテリアル株式会社(MMC)は、様々な分野で独自の研究開発を行う日本有数の技術チームと開発設備、長年にわたる知見と研究データを保有しています。
今後事業化が期待できる分野の開発テーマについて、新規事業の共同開発を視野に社外の皆様との協創を加速するアクセラレーションプログラムを今年も実施します。
SU全体の活動としては領域や時間にこだわらず、奔放な好奇心と蓄積された技術のままに、テーマの起案、推進を行っていますが、Wild Windではテーマの募集領域や当社から起案するテーマを毎年更新しています。
今年度は、特に「資源循環」と「GHG削減」という2つの領域からのテーマを募集するとともに、当社からは「熱電EMS」と「アレルゲン検出」という2つのテーマを起案いたします。
それらの事業協創に意欲のある方たちをパートナーとして募集します。
皆さまのご応募をお待ちしています。
私たちが興味を抱いている領域
過去に取り組んできたテーマ、現在進行中のテーマや事業をマッピングしてみました。
三菱マテリアル株式会社としては、下記以外にも、モビリティ、ヘルスケア、半導体にも注力しています。
図の中の ![]() ボタンを押すと詳細をご覧いただけます。
ボタンを押すと詳細をご覧いただけます。
![]() の2つのテーマは、Wild Wind 2025において、当社が起案し、協創パートナーを募集しているテーマです。
の2つのテーマは、Wild Wind 2025において、当社が起案し、協創パートナーを募集しているテーマです。
今年度は、2つの募集枠を用意いたしました。
1つは、特に「資源循環」と「GHG削減」という2つの領域において、新規事業テーマを提案いただけるパートナーの募集。
2つ目は、当社が起案しました「熱電EMS」と「アレルゲン検出」という2つのテーマの事業化に向けて協創していただけるパートナーの募集です。
それぞれに、検証期間等の日程に違いがあります。
以下に、それぞれの募集枠について詳しく内容をお知らせいたします。
特に「資源循環」と「GHG削減」という2つの領域において、新規事業テーマを提案いただけるパートナーを募集いたします。それら2つの領域そのものでなくても、それらに帰着すると思われるテーマについても、躊躇せずに応募いただきたいと思います。
募集領域の詳細なイメージは、“私たちが興味を抱いている領域” の “Wild Wind 2025” をご覧ください。
交流会においては、皆さまの考えているテーマを伺えるメンバーを揃えています。 Wild Windへの応募前に直接 Wild Wind 2025を推進しているメンバーと話しが出来る良い機会です。
プログラム説明交流会への参加もお待ちしております。
当社が興味を抱いている領域のなかでも特に注力したい領域(資源循環、GHG削減)に位置するテーマである『熱電EMS』と、注力したい領域に繋がるテーマである『アレルゲン検出』という2つのテーマの事業化に向けて協創していただける、意欲的なパートナーを募集いたします。
両テーマの位置する領域のイメージは、“私たちが興味を抱いている領域” の “Wild Wind 2025” をご覧ください。
交流会においては、両テーマの起案者も参加します。
Wild Windへの応募前に直接起案者と話しが出来る良い機会です。
プログラム説明交流会への参加もお待ちしております。
PoC費用はMMCにて一部負担。数百万/テーマ程度まで負担可能。
MMCの事業開発チームと共に4か月~6か月間の検証期間で事業化検討を行う。
Demo Day を通過見込みの案件について、ものづくり R&D 戦略部 または MMCイノベーション投資事業有限責任組合(CVC) からの出資可能性。
※CVCへのリンク:https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/business/rd/mmc_innovation.html
MMC の既存顧客との接点や検証設備について提供可能。
※既存事業との調整により提供できない場合もございます。
MMC と UNIDGE によるメンタリング伴走支援。
イノベーションセンターの材料およびその周辺技術に関するデータや知見 / 材料分析 / 解析設備を活用可能。
11月10日(月)~12月10日(水)
登記された法人としての応募であれば、企業/NPO/学校などの所属は問いません。
ただし、最長26年1月中旬~26年8月末までの期間にて、検証活動に必要な一定以上の稼働ができることが条件となります。
本ページの「Entry」ボタンより応募フォームに遷移後、必要事項を入力の上提出をお願い致します。
審査フロー:応募締め切り後、書類審査を実施し、1月上旬までに面談をさせていただきます。
審査結果通知: 書類及び面談結果は1月中旬までにご連絡致します。
以下のような企画は対象外となります。
MMC とのシナジー、事業の特徴性、事業案において活用可能な技術領域、経験・実績、今後の事業実現性や計画性などを鑑みて総合的に判断します。
新たな技術やサービスを活⽤したビジネスアイディアを幅広く募集しています。
三菱マテリアルの研究開発機能や要素技術、ネットワークなどのアセットが活用できるものであれば、事業領域は問いません。
三菱マテリアルならびにUNIDGEのアセットとリソースを活用した支援、メンタリングなどを中心とした支援を行います。
ただし、支援内容は確定・一律ではありませんので、個別に協議させていただきます。
応募いただいた皆様のアイディアは最大限尊重させて頂き、許可なく他に公開することはありません。
企業情報等を公開する際には、公開前に公開内容をご確認いただきます。
ただし、応募の段階から事業アイディア自体を秘匿することのみを目的とした守秘義務契約等の締結は想定していないため、秘匿とすべき情報については起案者の皆様自身で十分に扱いを気をつけて頂ければと思います。
審査会にて採択された後に、秘密保持契約などが必要な場合は、案件に応じて真摯に対応させていただきます。
複数社での連携による応募も可能ですが、連絡窓口となる代表機関を設定してご応募ください。
事業化検討状況を考慮した上で行うため、基本的にはDEMODAY/最終ピッチ以降となります。
出資は約束されたものではありませんが、DEMODAY/最終ピッチ 通過企業への出資は積極的に検討致します。
尚、出資を検討するにあたり、財務諸表等の提出をお願いすることがございます。
いいえ。プログラム説明交流会に参加していない方でも応募は可能です。









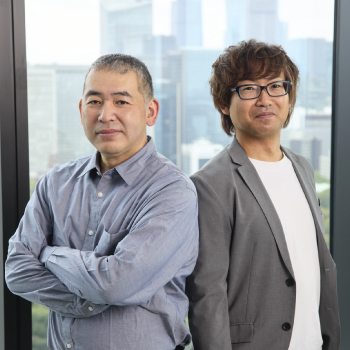








MMCは「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを目指す姿とし、 銅を中心とした非鉄金属素材、付加価値の高い機能材料や製品を製造する非鉄金属メーカーです。 高度なリサイクル技術による廃棄物の再資源化を通じ、「循環型社会構築」への貢献を目指しています。
UNIDGEは、大企業100社以上 / 12,000案件以上の新規事業の伴走支援実績があるAlphaDriveの オープンイノベーション支援に特化した戦略子会社です。私達は人とテクノロジーの力で 「協業」という選択肢を企業が当たり前に選べる世界を実現し、人や技術、企業の可能性を最大化していきます。