

加工事業カンパニー
自分のやっている仕事に
意味を見出せた瞬間、
人は飛躍的に成長する。
- N.H
-
加工事業カンパニー
開発本部 インサート工具開発センター1997年入社
※所属部署・役職、インタビュー内容は当時のものです

好きな研究を、
このまま終わらせたくない。


幼い頃から乗り物や機械いじりが好きで、身近な機械ものである自動車やオートバイをつくる業界に行きたいと考えていました。でも、突き詰めて考えた時、製造業の一番のベースは加工技術であるということに気づきました。
自動車メーカーでは自動車だけ、オートバイメーカーではオートバイだけにしか関われないのが基本だと思いますが、加工技術という職種ならばあらゆる産業に深く携わることができる。自分の興味のあるものを幅広く知るチャンスが増えることに、大きな魅力を感じたのです。そこで、学生時代は加工技術、その中でも今の仕事に直結する切削加工を専門に勉強しました。
その後就職活動する中で、当時の三菱マテリアル社員から「君が研究室で行っていることと同じ様な研究が、うちの会社でも行われているよ」と聞きました。当時、明けても暮れても研究に没頭していた私にとって、社会人になってもその研究を続けられるのは非常に魅力的な話でした。三菱マテリアルが切削加工業界で日本一であることは知っていましたし、普段から同社製の工具を使用していたこともあって愛着もありました。よし、ここに入社しよう。そう決意するに至ったのです。

あの時感じた
リーダーシップの重要性を胸に。


1997年に入社してから1年間、イノベーションセンターでCAEシミュレーションという切削工具の強度解析を担当。その時の研究をもとに製品化された「ディンプルバー※注1」は国内外で特許を取得し、大ヒットしました。その後、切削工具の開発部門へ異動。これまでに手掛けた製品は、今でも月に5億円以上の売上を上げています。
また、2010年から2013年までは、海外赴任を会社に直訴し、北米の販社でマーケティング業務に従事しました。以前から机の上で図面を描くだけではなく、自らお客様のところへ出向き、そこでの意見を製品設計に活かすということを信条にやってきた私でしたが、次第に出張だけでは飽き足らなくなっていました。「まだ若いうちに海外で本腰を入れてマーケティングを学んでみたい」という想いが強くなり、海外赴任を認めてもらったのです。そして現在は、グループリーダーとして開発部門へ復帰し、部下の育成と組織の強化を行っています。
そうしたこれまでの歩みの中で忘れられないのは、まだ一開発担当者だった頃。「切削工具の新製品シリーズ、約3,000アイテムを一気に開発する」という巨大プロジェクトのリーダーに抜擢されたことです。今まで先人たちが何度も失敗してきた壮大なテーマ。当時まだ若手で、それまでは分野が違う工具群を担当していたため、このプロジェクトを任された際は驚きましたが、経験や予備知識がない分、先入観を持たずに自由に取り組もうと考えました。
当時は対象物を削るインサートがそれを支えるホルダと一体になっている「本体一体型」の切削工具が主流でしたが、刃先であるインサートが欠損するだけで本体まで総取り替えとなり、経済的ではない点にお客様の多くが不満を持っていました。反対に、インサート取り付け部が交換式となっている「モジュラー型」は、破損時に先端だけ交換できるもののどうしても剛性が劣る。そこで、私たちは「モジュラー型ながら、本体一体型に匹敵する剛性を有する新工具」を開発することを目指しました。
目指すべき方向性が決まってからは、寝ても覚めても新しいアイデアをひねりだす毎日。なかなか思うように事が運ばない日々が続きました。そんなある日、自身の趣味であるオートバイ雑誌を何気なく読んでいると、ディスクブレーキキャリパーを通常の横方向からではなく、縦方向から固定することで取り付け、剛性を飛躍的に上げられるというラジアルマウント式キャリパーの記事を目にしました。「これだ!」この固定方法を応用すれば、どの方向からの切削抵抗にも強固に耐えうるモジュラー型工具ができる。そう確信した瞬間でした。
急ぎこの考えを具現化するべく、設計、試作から製品化に向けて取組みますが、またしても上手くいかないことが多く出てきます。これまで担当していた製品とは違い、開発陣だけで取り組むには限界がある。そこで、他部署の人々を巻き込み、チームを増強しながら開発にあたる方針に舵を切ることで何とか製品化に成功しました。その時、とにかく痛感したのがリーダーシップの重要性。このことを肝に銘じ、これまでの開発経験はもちろん、海外で異文化に触れた経験も活かしながら、理想のリーダー像を突き詰めていくんだという想いで、現在は日々の業務にあたっています。
※注1:インサートを取りつけるホルダ製品の一つ。対象物を深く削る場合、ホルダは長く設計されるが、その長さの為にたわみ、対象物を削る際振動が大きくなることが長年の課題だった。N.Hのシミュレーション解析により、それらの課題をクリアした形状のホルダが誕生した。
※注2:N.Hたちが開発した、“モジュラー型ながら、本体一体型に匹敵する剛性を有する新工具”「GYシリーズ」。(写真左)

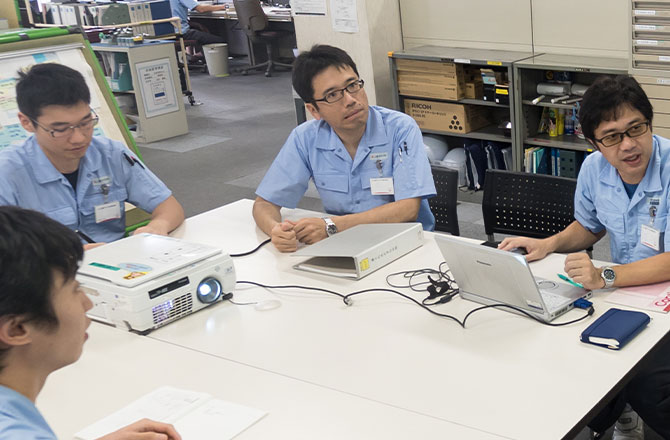

組織を伸ばし、
さらなる高みへ持っていく。


グループリーダーとしての責務。それは、エンジニア一人ひとりの能力を高め、組織力を強化していくことです。自分が直接図面を書くことはほとんど無くなりましたが、開発する工具を選定したり、カタログの中身を決定する役割は私が担っています。そういう意味では今も“ものづくり”は続いていると言えますし、一方で部下の成長を見るのもうれしいものです。
我々開発は複数の製品を同時進行で開発する関係上、個々の製品に開発担当者を設定しています。その担当者が製品のデザインを決めています。だから、「自由に楽しく製品に自分を表現してほしい。その製品が未来の名刺代わりになるのだから」ということは常々部下に伝えていますね。
部下を見ていて思うのは、段階的に成長する人間もいれば、何かをきっかけに急成長する人間もいるということ。自分が任された仕事に意味を見出し、モチベーションを持った瞬間に、人は大きくなるんだと感じています。
パッションを持った部下が更に増えれば、組織としての未来が広がるはず。私の想像を遥かに超えるような素晴らしい設計が部下から上がってくれるようになれば、会社としてもより高いレベルにいけるのではないかと期待しています。

 ある一日のスケジュール
ある一日のスケジュール
-
- 8:00
- ラジオ体操で身も心もウォームアップ
その後 組織の朝会でその日に行う業務の確認
-
- 8:30
- 時差があるためアメリカメンバーとTV会議もしばしば
-
- 9:30
- メールチェックおよびその対応
受信するメールの7割は海外から
-
- 12:00
- 昼休みは工場のまわりをウォーキングしリフレッシュ
その後ランチ
-
- 13:00
- 部下と新製品に関する打合せ
マネジャーではなく、エンジニアに戻れる瞬間
-
- 15:00
- マーケティング部、国内営業部と打合せ
-
- 16:00
- この頃になるとヨーロッパメンバーから電話が入る
おはようとこんにちはが交差する瞬間
-
- 17:00
- 海外に向けてメールを発信
日本が寝ている間に世界に働いてもらう
-
- 18:00
- 帰宅




